サイバー空間は賭博場ではない? それならオンラインカジノはどうなる? 単純賭博罪の「相手」はどこにいるのか――メディアの偏った報道に異議を唱える

近年、オンラインカジノの利用者が「違法賭博」で摘発されるケースが報道を賑わせています。しかし、こうした一方的な報道の中で、ある判決の存在がまったく顧みられていないことに、強い違和感を覚えます。
それが、福岡地方裁判所平成27年10月28日判決です。この判決が示した内容は、現在のネット賭博問題を議論するうえで、決定的に重要な視点を提供しています。
◆ 判決が示したこと:サイバー空間は「賭博場」ではない
この事案は、電子メールを用いて野球賭博が行われたケースでした。検察は被告に対して「賭博場開張図利罪」を適用しようとしました。しかし裁判所は、こう判断します。
「賭博場開張図利罪は、その犯人自らが主宰者となり、その支配下に『賭博場』すなわち賭博を行う一定の場所ないし賭博のための一定の場所的設備を提供し、その対価として寺銭等の名目の利益の取得を企図することによって成立する罪である。証拠によってその事実が立証されなければならない。」
そして続けてこう述べます。
「本件では、電子メールを通じてやり取りされていたにすぎず、胴元側が『その支配下に賭博場と評価できる場所や設備を確保して提供していた』とは評価し難い。」
つまり、「サイバー空間」は刑法上の『賭博場』には該当しないという明確な判断が下されたのです。
福岡地裁平成27年10月28日判決は、まさにこの点を問題にしました。事案は電子メールを利用して野球賭博を行ったというものでしたが、裁判所は、「賭博場開張図利罪は、その犯人自らが主宰者となり、その支配下に『賭博場』、すなわち賭博を行う一定の場所ないし賭博のための一定の場所的設備を提供し、その対価として寺銭等の名目の利益の取得を企図することによって成立する罪であるから、証拠によってその事実が立証されなければならない」が、本件では電子メールを利用して賭博が行われており、「胴元側が、その支配下に『賭博場』と評価できる一定の場所ないし場所的設備を確保してそれを提供していたと評価することは困難である」として、賭博場開張図利罪の成立を否定したのでした。検察官は、電子空間全体が〈賭博場〉に当たると主張しましたが、そのような主張は、「胴元と賭客が存在しさえすれば直ちに賭博場開張図利罪が成立することを認めるものにほかならず」、「移動可能な電子通信機器が発達した現代の賭博の実情に適合していない面があることは確かであるが、立法を経ずに解釈によって場所的要素を伴わない賭博主宰行為に処罰を拡大することは許されない」としたのでした。
刑法の条文で使われている言葉の意味を逸脱して処罰することは許されないという、刑法の大原則である罪刑法定主義からいえば、福岡地裁の判決はそのお手本のような判決だといえるでしょう。
◆ 判決の論理が正しいなら、なぜ「単純賭博罪」は成立するのか?
ここで疑問が浮かびます。
もし、サイバー空間は賭博場に該当しないとするならば、それを使って提供されるネット賭博行為について、「賭博場を開帳した」という罪が成立しないのは理解できます。
しかし、では逆に、ネットで賭け事に参加した日本人が「単純賭博罪」で有罪になるのはなぜなのか?
この点には、法律構造上の矛盾があります。
◆ 賭博罪は「必要的共犯」ではないのか?
刑法において、賭博罪は「必要的共犯」とされる犯罪です。すなわち、賭けをする者がいなければ成立しないし、逆に、賭けを提供する者がいなければ成立しない性質の犯罪です。
つまり、賭博をする者・させる者は対になっており、どちらか一方が不処罰であれば、もう一方のみ処罰するのは理論的に難しいというのが原則です。
ところが、現実にはこの「必要的共犯」の構造が無視され、海外サーバー上で運営されるオンラインカジノに参加した日本人利用者だけが「単純賭博罪」で立件され、有罪判決を受けているのです。
これは法理論的に整合的でしょうか?
◆ オンラインカジノの実態:相手は海外、空間はネット上
オンラインカジノの多くは、**海外で合法的に運営されており、外国のサーバー上にシステムが構築されています。**また、利用者がネットを通じて個人的にアクセスし、賭けを行うスタイルが主流です。
このような環境において、日本国内法で「胴元側」の存在を特定し、その賭博場性を論じるのは困難です。
では、日本国内にいる「プレイヤー」だけを摘発して有罪にすることは、公平性や法的一貫性の面でどうなのでしょうか?
◆ メディアが報じない、法の不均衡と曖昧性
こうした問題は極めて本質的であるにもかかわらず、メディア報道は「違法なオンラインカジノの利用者が摘発された」という表面的な情報ばかりを流し、その法的背景や判例との矛盾には一切触れません。
サイバー空間を法が想定していなかったことは明らかです。刑法が制定されたのは明治時代。インターネットどころか電話も普及していない時代の法制度で、現代の国境を越えた仮想空間上のやり取りを適切に取り締まれるはずがありません。
そのくせ、都合の良いときだけサイバー空間の行為を「違法」とし、一方で「賭博場ではないから無罪」という判決も存在する。このダブルスタンダードこそが、法の信頼性を損なっているのではないでしょうか。
◆ 法のアップデートとメディアの責任
今求められているのは、以下の2点です。
-
法制度の現代化:サイバー空間における賭博行為について、適切な基準と構造を再設計する必要があります。必要的共犯の理論も、ネット時代に即して再考されるべきです。
-
メディアの責任ある報道:一方的な違法認定や摘発報道ではなく、判例や法理論の背景を含めたバランスのある報道姿勢が必要です。
◆ 終わりに
「サイバー空間は賭博場ではない」と裁判所が明言した以上、オンラインカジノ利用者だけを摘発し続ける現在の運用は、法的にも倫理的にも再考を要するでしょう。
単純賭博罪の「相手」はどこにいるのか?
この根本的な問いに答えることなしに、ネット賭博の摘発だけを続けるのは、法の名を借りた恣意的運用にすぎません。今こそ、司法・立法・報道のすべてが、この矛盾に向き合うべきではないでしょうか。
おすすめ記事
コメント
この記事へのトラックバックはありません。






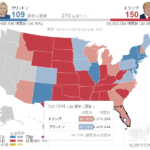




この記事へのコメントはありません。